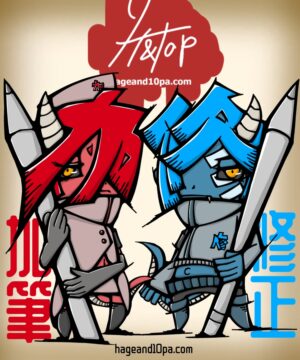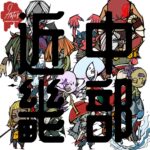ごきげんよう、ハゲと天パです。
引き続き、
四十七都道府県なんそれ妖怪図鑑
日本に伝わる数ある妖怪のなかで、
「なんそれ?」という妖怪をセレクトし、
47都道府県ごとに紹介するシリーズです。
にぎやかすのはおなじみのこの2人。
加筆です。
にぎやかします。
修正です。
しゃしゃり出ます。
2人(通称ペンドラゴンズ)についてはこちら。
※アフィリエイト広告を利用しています。
だってお金がほしいもの。
●第四十三回・熊本県
北海道 to 沖縄でお送りしております。
なんそれ妖怪図鑑 引き続き九州編。
前回は長崎県から、
大岩が崩れるような音でびっくりする怪異、
石投げんじょ(いしなげんじょ) でした。
石投げんじょ自体には、
さほど特筆することもなかったので、
「投石」について少し詳しくなれるブログでした。
今回は熊本県から、こちらの妖怪。

熊本代表 油すまし(あぶらすまし)

油すまし(あぶらすまし)は、
熊本県の天草市に伝わる妖怪。
メジャーなプレーヤー登場です。
鬼太郎にもたまに出てきますよね。
ゲゲゲの鬼太郎に出てきたら、
それはもうメジャーリーガーです。
作中では味方サイドの準レギュラーです。
まあ、そんなに大活躍するわけでもないので、
扱い的にはモブキャラですが。

そんな言い方やめて。
油すましの初出としては、
昭和初期の郷土史家・浜田隆一氏の著書
「天草島民俗誌」。
ここでは「油ずまし」となっていますが、
「油すまし」と濁らずに、すました感じで表現するのが一般的ですね。
「天草島民俗誌」によれば、
熊本の天草郡栖本村字河内と下浦村
(いずれも現・天草市)を結ぶ、
草隅越という峠道にて、
おばあさんが孫を連れて通ったとき、
「ここにゃ昔、油瓶さげたん出よらいたちゅぞ」
と、ばーちゃんが孫に話していると、
「今もー出るーぞー」と言いながら、
油ずましが現れたとか。
以上。
以上!?
そんだけなの?
実際、それ以外には伝承が少なく謎の妖怪です。
これぞ「なんそれ妖怪」ですよ!
すっかりおなじみになっております、
民俗学者・柳田國男の著書「妖怪談義」
アブラスマシの項では天草島民俗誌を引用して
紹介しているものの、この「怪物」が何者で
どのような外観なのかは一切記述なしです。
ちなみに原典の天草島民俗誌では、
「油瓶をさげた怪物が出た」ではなく、
「油瓶さげたん出よらいた」と述べられており、
「妖怪・怪物」とは言っていないのです。
つまりただの、
油瓶を下げた人間だった可能性も?

積み上げるミステリアス。
とんだがっかりミステリアスだな。
ちなみに「妖怪談義」では、
「ツルベオトシ」「ヤカンヅル」「サガリ」
といった頭上から物が落ちてくる怪異と、
並べて紹介されており、
妖怪研究家・京極夏彦氏によると、
油すましとは人の姿をした妖怪ではなく、
釣瓶落としなどと同様に
「油瓶が頭上から下がってくる怪異の可能性がある」と指摘されているそうです。
熊本ではこの油すましと同様、
「妖怪の噂話をするとその妖怪が現れる」
といった怪異譚が他にも伝えられているそうで、
天草郡一町田村益田では、
「うそ峠」という嘘みたいな名前の場所を
通りかかった2人連れが
「昔ここに、血のついた人間の手が落ちてきたそうだ」
と話すと、
「今もー」
と声がして、血がついた手が坂から転がり落ち、
逃げ切った後に
「ここでは生首が落ちてきたそうだ」
と話すと、また
「今ああ……も」
と声がして
生首が転がり落ちてきたそうです。
いや、もうわざと言ってるじゃん。
下益城郡豊野村(現・宇城市)でも、
「今にも坂」という今にも出そうな場所があり、
ここでは大入道が現れるそうですが、
その話をしながら坂を通ると、
「今にも」と声がして大入道が現れるとか。
今もいるぞ系の妖怪は、
自分の存在を過去のものにしたくないんでしょうね。
過去に一発当てた芸能人みたい。

悲しくなるからやめて。
一発あたったら贅沢せずに、
手堅い投資とかに回すのが正解だと思います。
まあ、オルカンの投資信託とか
NISA枠で買っとけば間違いないんじゃないかしら?
うん、手堅いと思う。

上記の通り、
そもそもは情報が極端に少ない妖怪でしたが、
昭和以降の妖怪関連の書籍においては、
全身に蓑を羽織った、すました顔の妖怪。
油の入った瓶を持ち峠に突如出現して通行人を驚かせる。
という説明がよくされます。
これは、水木しげる御大が描いた妖怪画のデザインが一般化したもので、
本来の伝承とは無関係なものではあるものの
御大の功績は非常に大きいですね。
私もこのデザインがすごく好きで、
昔、油すましグッズを集めようと思ったくらいですよ。
集めなかったけど。

集めなかったのかよ!
ミニマリストなんで。
ちなみに、妖怪画の顔のモチーフは、
文楽の「蟹首」という人形の頭という説があるそう。
もはや水木先生自体が伝説です。
油すましの正体については
「油を盗んだ罪人の亡霊」という設定があったり、
書籍によっては、すまし顔をしているので
「すまし」という名前の由来としているとか。
ただし、お察しの通り、そういった伝承はないです。
また「頭脳派妖怪」とされていることもあり、
映画「妖怪大戦争」で油すましが参謀格だったことによるそうです。
キャラ付けがやりたい放題だな。
まあ、いいイメージだからいいんじゃない?
正体について、
ミステリアスを積み重ねた油すましですが、
2004年、天草市栖本町河内地区で、
首のない石像が両手を合せた姿の、
「油すましどん」と呼ばれる石像の一部が発見されたそう。
元は栖本町中の門・すべりみちという場所に
安置されていたものが移転されたもので、
かつては子供がこの「すべりみち」で
遊んでいると「油すましどんが出る」と
言って恐れたと地元の伝承者の方は語っているとか。
また、地元では「油をしぼる」ことを、
「油をすめる」と表現したそうで、
油絞りの職人が祀られて神になったものが、
時を経て妖怪に変じたという説もあるそうです。
謎の存在は興味がつきませんね。
そんなわけで熊本県から、
油すましでした。
お城あり、大自然あり、
温泉あり、おしゃれな街もありな熊本県。
いいところです。
次回は大分県の妖怪です。
このブログは、
気になったことを調べ、
学んだ内容とイラストを紹介するお絵描きブログ。
ソースは主にWikipediaなどになりますので、
学術研究ではなくエンターテイメントとしてお楽しみください。
興味のきっかけや、ふんわりしたイメージ掴みのお手伝いになればうれしいです。
油すまし-wikipedia
熊本もおいしいものがたくさんですが、
馬刺しははずせませんね。
熊本は馬肉生産量日本一で、
馬刺しや馬肉の専門店が豊富。
諸説あるものの、熊本藩初代藩主加藤清正公が、
朝鮮出兵の折、兵糧が尽きて困った結果、
仕方なく軍馬を食べたら美味しかったので、
帰国後も好んで食べたのが始まりだとか。
肉を切った切り口が、
きれいな桜色なので「桜肉」といわれ、
おろしショウガやおろしニンニク、
刻みネギなどを薬味に、
九州の甘い醤油でいただきます。
本場のおいしさをどうぞ。
じゅるり。
ウチの子たちもおすすめです。↓
 | 価格:5980円 |

さっぱりした旨みとほのかな甘みが魅力です。
suzuriでオリジナルグッズ始めました!↓↓↓

FXを始めるチャンスなんじゃないですかね?↓
ふるさと納税 はじめませんか?