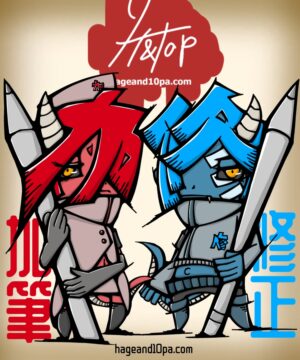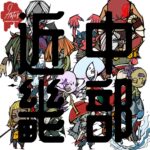ごきげんよう、ハゲと天パです。
ついについに今回で、
四十七都道府県なんそれ妖怪図鑑
ラストです。
日本に伝わる数ある妖怪のなかで、
「なんそれ?」という妖怪をセレクトし、
47都道府県ごとに紹介する試み。
にぎやかすのはおなじみのこの2人。
加筆です。
にぎやかします。
修正です。
しゃしゃり出ます。
2人(通称ペンドラゴンズ)についてはこちら。
※アフィリエイト広告を利用しています。
だってお金がほしいもの。
●第四十七回・沖縄県
まずはおさらい。
北海道 to 沖縄でお送りしている
なんそれ妖怪図鑑。
前回は鹿児島県から、
イッシャ(いっしゃ) でした。
トウモロコシのようなしっぽを持ち、
おだてるとすごい魚とか取ってくれる妖怪。
ただし、下手に関わると、海水を飲まされたりしますのでご注意。
最終回をかざるは沖縄県。
代表するのはこちらの妖怪。

沖縄代表 飯笥(みしげー)

飯笥(みしげー)またはミシゲーマジムンは
沖縄県に伝わる妖怪。
現地でいうところ、悪霊、妖怪を総称して
「マジムン」といいますが、その一種。
本来の「飯笥」はしゃもじのことですが、
古くなったしゃもじが妖怪に変化したものが
この飯笥(ミシゲーマジムン)になり、
いわゆる付喪神(つくもがみ)というわけです。
付喪神についても説明しておくと、
長い年月を経た道具などに精霊(霊魂)が宿ったもの。
九十九(つくも)神と表記されることもあり
おばあさんの白髪をあらわした言葉、
「つくも髪」とかけて「長い時間(九十九年)」を示しているんだそうな。
室町時代の御伽草子系の絵巻物でその名も、
「付喪神絵巻」
という直球タイトルの書物があり、
それに記された物語によると、
器物は百年経つと精霊を宿し付喪神となるため、
人々は「煤払い」と称して毎年立春前に古道具を路地に捨てていたとか。
廃棄された器物たちはプンプン腹を立て、
節分の夜に妖怪となり一揆を起こしますが、
人間や護法童子に懲らしめられ、最終的には仏教に帰依する。
というお話。
結局、仏教アゲにつながるパターン。
仏教の懐の広さね。
物語のなかでは、
「百年で妖怪になる」とされていますが、
厳密に100年の期間が必要というわけではなく、
人間も草木、動物、道具などなど、
万物は古くなるにつれて霊性を獲得し、
変化する能力を獲得するに至る。ということを示しているそうです。
飯笥(みしげー)に話を戻しますと、
やっぱり時を経て古くなったしゃもじが霊性を得て
夜中に動き出しで騒いだり、人をからかったりと
イタズラをはたらくんだとか。
なお、特に人に害をなすことはないようです。
ちなみに、しゃもじ妖怪のみしげーの仲間に、
杓子(おたま)が妖怪になった
鍋笥(なびげー)もおり、
捨てられた食器類は夜になると遊びだし、
ごみ捨て場から音楽が聞こえてくるといいます。
なんだか楽しそうではありますが、
やっぱり怖いので、
「古くなった飯笥や鍋笥は捨てるものではない。」
といわれていたそうです。
ともあれ楽しそう。
付喪神的な
「捨てられた恨み感」
は少なめよね。
そんな沖縄の付喪神、飯笥の伝承はこんな感じ。
ある夜、
楽器の音色を聞いた男が家から出てみると、
若い男女が広場で遊んでいたとか。
これは楽しそうだと、賑やかさに誘われて
男も仲間に加わり、飲んだり踊ったりして一晩中過ごします。
夜が明けてパーティーはお開きになり、
男は疲れてその場で眠ってしまいますが、
目が醒めたとき、彼の周辺にはしゃもじやおたまなどの食器が散乱していたとか。
これはつまり、捨てられた食器類が夜中にパーティーしていたのだそうです。

騒ぐのはたのしーからねー。
またこんな話もあります。
ある農夫が夜、
道にうずくまっている牛を見つけ、
自分の家へ連れ帰って牛小屋へ入れ、餌をあげるとよく食べました。
翌朝に小屋を覗くと牛の姿はなく、餌が積み上げられた上にしゃもじが乗っていたとか。
はたまたは、こんなのも。
夜中、ある家の扉を何者かが叩きまして、
家の人が扉を開けてみると、人の姿はなく、
代わりに1本のしゃもじが倒れていたとか。
シンプル。
何がしたかったんだろね。
きっと人をからかいたかったのね。

きっと、そういうことさー。

なお、皆様おなじみのしゃもじ。
漢字で書くと(杓文字)。
ご飯をすくったり混ぜたりするのに使用する道具。
杓は杓子の杓でわかりますが、
文字ってなんなん?って感じですよね。
この「文字」、室町時代初期頃から宮中や院に
仕える女性(女房)が使い始めた
女房言葉(にょうぼうことば、女房詞)
と呼ばれるものによるものだそう。
語頭に「お」を付けて丁寧さをあらわしたり
語の最後に「もじ」を付けて婉曲的に表現するものとのことです。
お箸、おうどん、お砂糖、お塩など、
「お」は今もよくつけますが、
「もじ」は今はあんまりつけないですね。
ともあれ、
杓子の「しゃ」に「もじ」をつけたのが、
「しゃもじ」の由来になります。
ということは、
「おしゃもじ」はすごい丁寧ってこと?
用法として正しいのかは謎ですが、
きっと丁寧フルマックスなんでしょう。
なお、杓子には板状の箆(へら)杓子と、
刳(くり)物の汁杓子がありますが、
もとは汁をよそう汁杓子もご飯をよそう飯杓子も
どっちも「しゃもじ」でしたが、時代が経るにつれ、
汁用のものをおたま(お玉杓子)、
米飯用のものを「しゃもじ」というようになったそうです。
まさかシリーズの最後が、
しゃもじの話題とはね。

あぎじゃびよー。
そんなわけで、
しゃもじで締めるとは予想外でしたが、
なんそれ妖怪図鑑、ラストの沖縄県でした。
はたしてこれで良かったのか・・・
次回はとりあえず、中四国・九州編のまとめになります。
どうもありがとうございました。
新シリーズもよろしくお願いします。
このブログは、
気になったことを調べ、
学んだ内容とイラストを紹介するお絵描きブログ。
ソースは主にWikipediaなどになりますので、
学術研究ではなくエンターテイメントとしてお楽しみください。
興味のきっかけや、ふんわりしたイメージ掴みのお手伝いになればうれしいです。
飯笥-wikipedia
マジムン-wikipedia
しゃもじ-wikipedia
女房言葉-wikipedia
今回は沖縄の
名物料理をご紹介。
ジーマミー豆腐
めちゃおいしいよね。

あい、ふるさと納税の出番だねー。
ウチの子たちもおすすめです。↓
 | 価格:7000円 |
落花生の絞り汁に、
芋くず(サツマイモデンプン)を加えてつくる沖縄の郷土料理。
もちもち食感がおいしいです。
豆腐といっても
大豆じゃないんだね。
沖縄県では出汁のタレ以外に、
黒糖味、紅芋味、チョコ味など色々な甘い味のものも販売されており、
みんなだいすきなデザート的存在ですね。
本場の味をぜひご家庭で。

うさがみそーれー。
「召し上がれ」
とのことです。
 | 価格:2000円 |
suzuriでオリジナルグッズ始めました!↓↓↓

FXを始めるチャンスなんじゃないですかね?↓
ふるさと納税 はじめませんか?